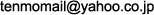2006年08月29日(火)
木に飲み込まれる電線 [タイで生活]
今朝オフィスに続く電線がソイの脇の木々に飲み込まれそうになっているのを発見。
このまま放置したら木の成長とともに電線が引っ張られて切れてしまうのではなかろうか、と心配になった。
ところでモーリさんは相変わらずパパイヤ茶を作ってくれるが、最初の頃は加減して少しだけ入れていたパパイヤの量が最近大胆になってきたようだ。
お茶の香りしかしなかった初期のパパイヤ茶と比べて今のは得体の知れない香りと味がするようになった。
正直まずい。
でも、このまずさが「体にいいものを摂取している」という健康オタク心をいい具合にくすぐってくれる。
Posted by てんも at 10時37分 パーマリンク
2006年08月28日(月)
若さの秘訣 [タイで生活]
海の見える大きな公園に名言集が刻んであった。
何気に眺めていたら、面白いのがあった。
The secret of staying young is
to live honestly,eat slowly and lie about your age.
Lucille Ball 1911-1989
正直に生きろと言いながら、年齢については嘘をつけという、素敵な格言である。
この人のことは知らなかったが、一体どんな人だろうと調べてみたらルシル・ボールまたはルーシー・ボールと呼ばれるアメリカのコメディアン女優なのだそうだ。
ご本人も確かに長生きしている。
私もこれからは自称27歳でいこうかと思う。
・・・さば読みすぎ?
Posted by てんも at 00時06分 パーマリンク
2006年08月27日(日)
スーパーのレジの謎 [タイで生活]
むかーし昔、まだ学生だった頃にアルバイトでコンビ二の店員をしていたことがある。
そこで教えてもらった商品の袋詰めは今でも日本のスーパーで買い物をした時に役に立つ。
基本は牛乳など大きいものを先に入れること。重いもの、大きいものから順にかごから取り出し、バーコードを読み取った後に袋に入れていく。一連の流れがスムーズにできるようになれば一人前なのだ。
タイの地元スーパーでは今でもお客さんに商品をかごから出してレジ台に乗せることを要求するところが多い。レジ台にズラーッと並んだ商品の中から似たような商品を選んで袋詰めしてくれる。袋詰めをしてくれるのはありがたいのだが、どうしてレジ台に商品を全て出さないと袋詰めできないのか謎である。
かごから出してまた袋に詰めるのであれば、かごから直接袋に詰めた方が効率がいい。だから私は商品が少ない時などかごをレジ台ノ乗せてしまうのだけれど、レジ係はやはりかごを傾けて全ての商品をかごから出して、そこから袋詰めをはじめる。先日は
「かごから商品を出してください」
と注意された。
商品をレジ台に並べるのはあくまで客の仕事になっているようだった。
そういえば私がタイに来たばかりの時はかばんの持込禁止のスーパーが多かった。客の万引きを防止するために最初から客にかばんを持たせないのだ。スーパーに入場する前にかばんを預けるコーナーがあって、そこで番号札と交換にかばんを預かってもらうシステムだった。店内に持込を許されるのはお財布と携帯電話だけ。
それが外資系のスーパーの進出とともにかばんも自由に店内に持ち込めるようになった。
あと数年もすれば、レジのシステムも変化して、お客さんはレジ台にかごを乗せるだけで良くなるのかもしれない。
Posted by てんも at 08時50分 パーマリンク
2006年08月26日(土)
あれってもうあれしたっけ [タイで生活]
物の固有名詞が出てこなくて「あれ」で代用してしまうことが多くなった。これって、まずい傾向じゃ・・・。
ひどい時など、「あれってもうあれしたっけ?」と聞いている。これでは聞かれた方も答えようがない。
これってやはり非常にまずいんじゃ・・・。
意識して「あれ」の使用をやめるようにしているけれど、気を抜くとすぐ「あれ」を使ってしまう。「あれ」を使わないで話をすることを苦痛に感じたりする。
ここはやはり、先日うっちさんに見せていただいた「脳が若返る」ゲームを早々に入手すべきかもしれない。
Posted by てんも at 07時46分 パーマリンク
2006年08月25日(金)
子供と親の関係 [タイで生活]
先日モーリさんが1冊の本を薦めてくれた。
「とても良い本だからぜひ読みなさい」
と言う。
いつか読もうと思いつつ
「はーい」
といい加減に返事をしたら、きっと読まないだろうと思ったらしい。(鋭い勘である)その場で本の概要を説明してくれた。
母親は何人もの子供を育て面倒を見ることができるのに、何人もいる子供達は自分達が大きくなってからたった一人の母親の面倒さえ見ることができない。
という内容だった。
たしかにそうだな、と考えさせられる話だった。
モーリさんもおばあちゃんの面倒を見ていた。近所の学校で教員の仕事を続けながら昼休みには家に戻りおばあちゃんにお昼を食べさせるという生活を長年の間続け、最後を看取った。
友人のお母さんの話も私にはとても驚きだった。
友人は5人兄弟の末っ子に生まれた。その友人が小さい頃にお父さんが亡くなった。その後お母さんは一人で子供達を育て、さらに夫の父親、友人にとっては祖父にあたる人を家に呼び、実の親のように面倒を見て最後を看取った。
このお母さんは自分の子供のほかにも親戚の子供やら孫やらも面倒を見る子育てのプロで、優しく包容力のある人。今はもちろん子供や孫に大切にされている。
本当に何で、人は自分の子供ならお風呂も食事も喜んで世話をするのに、年老いた親世代の世話はあまり喜んでできないのだろう。
私も、モーリさんや友人のお母さんのように包容力のある人になりたい。
Posted by てんも at 10時54分 パーマリンク
【 過去の記事へ 】